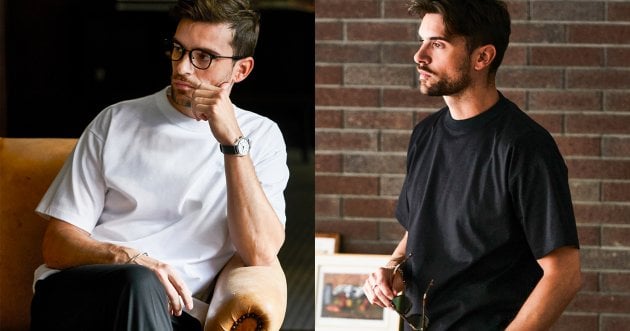ジーンズ好きなメンズなら、高い品質が海外でも評価される「岡山デニム」は当然ご存知のはず!デニム生地を一貫生産する「カイハラ」や「クロキ」といったデニム生地メーカーから、「桃太郎ジーンズ」のようにジーンズメーカーまで、多くのメーカー抱えています。しかし、そもそもなぜ岡山でジーンズ産業が栄えたのか気になりませんか?今回は岡山ジーンスが産業として成長してきた背景を紹介していきます。 IMAGE:okayamadenim.com
スポンサーリンク
綿花の栽培が盛んな児島地区「米つくりの代わりに..」
倉敷市児島といえば、もともとはその名の示すとおり島でしたが、 江戸時代初期に干拓によって本土と陸続きとなりました。しかし干拓地の新田は、もともと海だったことから塩気があり米作りには適さない環境でした。そこで塩気に強い綿花の栽培がはじまり栄えたという歴史的な背景があります。
藍の栽培、藍染めに強い「ジーンズのふるさと、井原地区」
weblio児島と同じく、綿花の栽培が盛んだった井原地区。それに加えて、デニム生地には欠かせない「藍の栽培〜藍染め」を江戸時代から得意とする地域でした。参覲交代で行き来する武士たちの間で「井原の藍染厚地織物」が当時から評判になっていたといいます。国内向けだけではなく、大正元年以降は「備中小倉」としてオーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ、アジア、欧米諸国に輸出されるなど世界中で重宝されてきました。
学生服・作業服製造の岡山。裁断・縫製に強い
学生服縫製ニシキ岡山といえば、江戸以降は厚地織物の産地として、大正以降は学生服の製造で全国トップシェアを握ってきたことで知られています。作業服はいわずもがな、学生服についても「学生が3年間ほぼ毎日着用する」という耐久性を求められる分野。高度な縫製・裁断ノウハウを有しているというわけです。
国産ジーンズ第1号が生まれた地「児島」
bigjohn昭和27年以降、学生服の生地が急速に綿から合繊に切り替わっていきました。困窮した非・合繊の生地工場や縫製工場が「次なる活路」としてジーンズの製造に打って出たことが「デニムの岡山」が誕生したきっかけと言われています。昭和40年(1965年)4月、ビッグジョンの前身であるマルオ被服が発売したジーンズこそが国産ジーンズ第1号だと言われています。国産ジーンズとは言うものの、完全に0からのスタートだったため、実はデニム生地はキャントンミルズ社からの輸入で「CANTON」ブランドとしての発売でした。一方で織物生地メーカーも昭和35年頃からデニム生地の生産をはじめていきました。
ジーンズ作りに必要な紡績以外の工程がすべて県内で完結。若手の参入で洗練された、脱アメカジのジーンズも登場
fagassent岡山では、ジーンズ作りに必要な「綿花栽培」「紡績」「染色」「織布」「縫製」「洗い加工」などのうち「紡績」以外の工程については、すべて県内で完結させることができます。各工程に強みをもった工場同士が連携することで作り出されるジーンズやデニム生地は海外でも高い評価を受けています。特にデニム生地に関しては「カイハラ」や「クロキ」が世界的に有名で「一流メゾンブランドで岡山デニムを採用していないところはない」とまで言わしめています。
製品の方では、良くも悪くも昔ながらのアメカジテイストのジーンズが多いですが、最近では若手の参入も相次いでおり、より洗練されたデザインのジーンズがリリースされています。デザイナー青木俊樹氏が立ち上げたFAGASSENT(ファッガセン)などは最たる例です。今後ますます目が離せない岡山デニム、ぜひ目を向けてみてはいかがでしょうか。